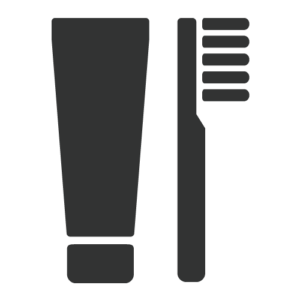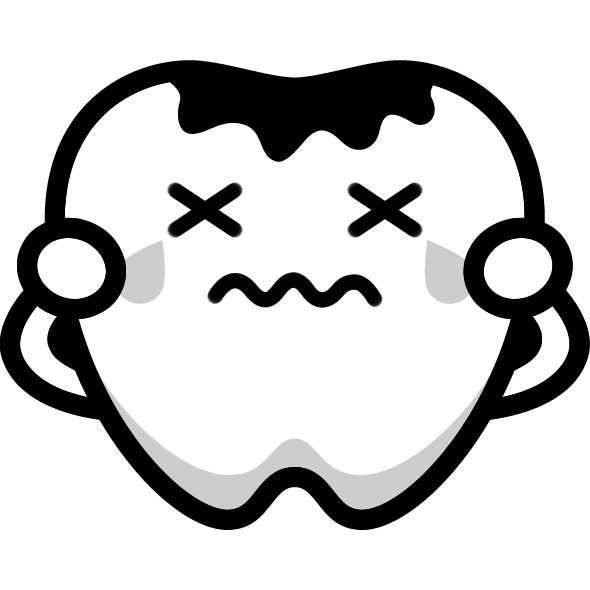
酸蝕歯
こんにちは、みなと歯科です。
近年、むし歯や歯周病に続く第3の歯の疾患として「酸蝕歯」が増加していることが注目されています。
現在、国民の4人に1人が「酸蝕歯」に罹患しています。
歯の表面のエナメル質は、人体で最も硬い組織のリン酸カルシウムでできていますが、強い酸にさらされると分解され溶けてしまいます。
この状態を「酸蝕」と呼びます。
「酸蝕歯」の原因
① 酸性の食品や飲み物(外因性)
レモン、グレ-プフル-ツ、炭酸飲料、スポ-ツドリンク、ワイン、黒酢、柑橘系ジュ-ス
最近の健康志向によるビタミンC含有のサプリメント、ビタミン剤等
② 胃酸の逆流(内因性)
逆流性食道炎、摂食障害(過食症、拒食嘔吐)、アルコ-ル依存症などにより胃酸が口腔内に逆流することがあります。
胃酸は強い酸性なので注意が必要です。
③ 唾液の分泌不足
ドライマウス(口腔乾燥症)などで唾液の分泌量が減ると、口腔内の酸性が強くなり酸蝕歯が進行します。
「酸蝕歯」の症状
① 歯のエナメル質が薄くなり、歯が透明になってきます。
② 冷たいもの、温かいもの、甘いものがしみるようになります。
③ エナメル質が溶けて歯の強度が低下して、物理的な力で欠けたり割れたりします。
私たちの口腔内は、中性のpH7前後に保たれていますが、飲食物や胃酸の影響で
pH5.5以下になると歯は溶けやすくなります。
「酸蝕歯」の対策としては
① 酸性の飲食物を口にした後は水で口をゆすぐ。
② 酸性の飲食物をダラダラと食べたり飲んだりしない。
③ 就寝前に酸性の飲食物を控える。
④ 酸性の飲食物を摂取した直後はエナメル質がやわらかくなっているため、30分経って歯みがきする。
⑤ 唾液の分泌を促すことが大事で、唾液は酸を中和して歯を守ります。
水分を摂る、ガムを嚙む等の唾液の分泌を促すことを意識しましょう。
私たちの歯は年齢を重ねるほど、酸蝕の影響を受けやすくなっています。
「酸蝕歯」は、むし歯や歯周病に続く第3の疾患だということを認識して、定期的に歯の健康状態をチェックすることは大切なことです。
痛いところを治すだけではなく、いつまでも自分の口で食べられるよう管理栄養士を含めた多職種連携で長いお付き合いを目指しています。港南台で皆さまに寄り添うアットホームな歯科医院をお探しの方はみなと歯科へ!